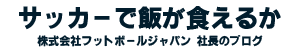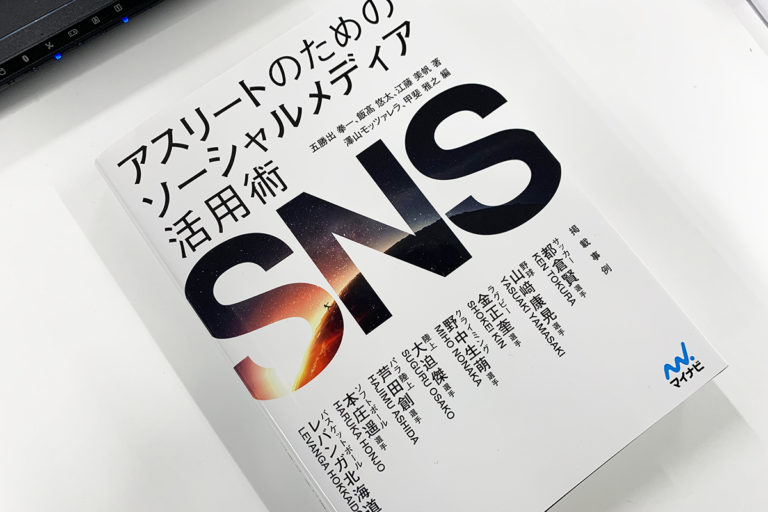皆さんこんにちは、フットボールジャパンの原島(@harashi10)です。
先日、『アスリートのためのソーシャルメディア活用術』という本を読みました。
いつかスポーツ選手やチームのSNS活用については書きたいと思っていたので、弊社事業の事例を含め、私のキャリアを通じて感じた、メーカー(スポーツウェア)視点でのスポーツ選手やチームのSNS活用について書いていきます。
スポーツ選手(チーム)はSNSをやるべき
書籍内にもありますが、私もスポーツ選手(チーム)はSNSを活用する以外の選択肢はないと考えております。
私自身、起業前に背中を後押しした大きな要因の1つがSNSでもあり、ビジネスマンも含めて多くの方が活用すべきだと考えています。費用もかからないですし。
選手単位ではなくチームで見た場合も、私がチームのマーケティング等の担当者であれば、全選手にアカウントを作ってもらってガイドラインの基で運用します。
それくらい必須のものだと考えています。
SNS活用が必要な理由
どうしてSNSを活用した方がいいか。
書籍ではMarket VALUEと表現されておりましたが、市場価値が高まる=収益に繋がる or 増える可能性があるため。
私はここが大きいと考えています。(※書籍にもありましたが、プレーヤーとしての価値がまず最優先)
私が近しい選手やチームへ話をするときは、視聴率という言葉に例えますが、選手(チーム)が(特にウェブ上で)どれくらいの数字を持っているか。ここが大事だと考えています。
弊社事業ではスポーツ選手、チームの他、イベント主催の団体などからも、協賛やスポンサードの相談を受けることが多々ありますが、必ず質問しているのが視聴率です。
スポンサー・協賛時の重要な判断軸
『競技カテゴリー上位で、視聴率が100のA選手』と『競技カテゴリー下位で、視聴率1,000のB選手』
この2選手を数値だけで判断した場合、B選手の方が広告価値があるとも考えられ、協賛する(協賛額が増える)可能性が高くなることもあり得ます。
メーカーではアプローチできない人たちへ、どう認知してもらうかが課題で、弊社事業の場合は、サプライやスポンサードのゴールはウェブサイトへの流入数増加と考えています。
※流入後、ウェアの購入に繋がるかは弊社側の課題という考え方です。
流入数次第では、契約更新時、次の企画の時などにより大きな協賛やスポンサードを検討するのは自然のことで、アスリートとしての価値の他、視聴率ベースの広告価値が判断の大きな要因となります。
PRとの相性の良さ
アスリートとSNSの関係で相性がいいと私が考えているものが2点。
まず、選手活動に必要なもの(商品、サービス)はほとんどがSNSでの発信と相性がいいと考えています。
アスリートにとって当たり前のものが、アスリート以外の人には当たり前ではないことは多々あります。
競技用ウェア、シューズ、その他競技に必要なアイテム、食事、トレーニンググッズ、ケア方法など、アスリートが使っているものがどんなものなのか、知りたい人は多いはずです。
スポーツは成果が目に見えてわかりやすいので、アスリートのレビューは根拠も◯で、購入の判断にあたえる影響力も大きいことが想定されます。
もう1点は後発のスモールビジネスやプロダクトと、アマチュア・セミプロカテゴリーのアスリートは取り組みやすいという点。
弊社事業は、広告予算がない中で立ち上げ・スタートしましたが、3年目くらいまでは自社アカウントと、選手のSNS流入を主要プロモーションに据えておりました。
一緒に成長していくような取り組みにできると◯ではないかと考えています。
PRにおいてどんな投稿がいいのか
メーカー視点で見た場合、スポーツ選手(チーム)のSNSによるPR発信はどのようなものがいいか、私が考えていたものと同じイメージの事例が書籍でも取り上げられていました。
考え方としては『アスリート活動の延長上、自然なシーンの中に(スポンサーが)溶け込んでいること』です。
書籍から気になった事例
書籍ではクライミングの野中生萌選手のインスタグラムが取り上げられていて、気になって拝見したところ、練習風景など選手・メーカーおたがいの世界観を壊すことのない自然な投稿が多く見られました。
この投稿をInstagramで見る
例えば『〇〇の〇〇がオススメです!』というようなストレートな投稿の場合、メーカーのPRが透けてしまい、何より選手を応援してくれているファン、サポーターに対して、世界観を壊してしまい、(双方の)マイナスイメージになりかねないのかなと。
PRやライティングを勉強することは、セカンドキャリアに向けて決して不要なものではなく、プラスになる点も多いはずです。
ただ、それは選手活動の延長ではないので、貴重な時間を奪ってしまうことも懸念されるので、選手活動の延長に溶け込んでいることが発信しやすさも含めて◯ではないかと考えています。
個人的な感覚の話ですが、最近ではSNS上にPR感の強い投稿が増えてしまったなという印象です。
これはメーカー側の設計や依頼方法にも大きな責任があるという印象で、弊社でも気をつけないといけないなと思っている点です。
PR以外の投稿は
プライベートや面白い(おふざけ)系の投稿、スキル紹介などを喜んでくれるファン、サポーターもいるかと思いますが、私はアスリートとして目標に向かって頑張っている姿の発信がベストではないかと考えています。
書籍内では『ビハインドザシーン』として、練習やケガからの復帰を目指すシーンが取り上げられていましたが、それらを含めたストーリーこそが、コピーできない選手(チーム)が持つオリジナルコンテンツでかつ、圧倒的な共感を生み出すものではないかと。
フットサル領域では、書籍にも取り上げられていたFC NAKAIというチームが、YouTubeで『Fの頂き』という企画を展開していましたが、これはストーリー性で大きな共感を集めた好事例だったと思います。
熱量は高いところから低いところへ伝わる。スポーツは特にその世界観が強いのはイメージしやすいですよね。
それとスポーツは動画との相性も◎なので、ショート動画が増えてきた最近のSNSの状況も、追い風になると考えています。
取り組んでみたいこと
書籍内でアスリートとファン・サポーターの関係作りやファンムーブメントについても触れられていましたが、弊社事業でもSNSを活用したプロモーションはこれからも展開していきたいと思っています。
基本的にはやはり『アスリート活動の延長にあること』で、結果『メーカーが選手の活動をサポートできる』『ファンの方が喜んでくれる』ことが重なる領域、そして『メーカーの認知アップに繋がる』企画にしたいと考えています。
以上、私がこれまでのキャリアから感じているアスリートのSNS活用についての解説でした。
紹介した書籍『アスリートのためのソーシャルメディア活用術』は、近しい選手・知人には私がすべて自己負担して提供してもいいと思えるくらいの内容でした。
チームなら1冊購入しておいて、読み合わせの機会を作ってみるのも面白いのではないかなと思います。
関連リンク:アスリートのためのソーシャルメディア活用術